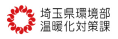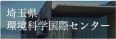2025-06-17
#8「温故知新 打ち水と雨水利用」

6月上旬、さいたま新都心で開催された「さいたま打ち水大作戦2025」に参加しました。例年は7月の梅雨明けの開催ですが、参加する子どもたちの熱中症リスクを考慮して、今年は梅雨入り前となりました。水のイベントとして6月上旬では気温が低すぎないかと不安もありました。いざ蓋を開けてみると、なんと日向は30℃を超える暑さで、結果的には打ち水日和となりました。季節変化を見通すのが益々難しくなってきた今日この頃です。これも気候変動の影響でしょうか。
打ち水は涼を呼ぶ昔ながらの風習です。直射日光などで温まった地面に水を撒くことで、水が蒸発し、その気化熱が温度を下げるようです。その効果は一時的なものではありますが、温暖化の影響ばかりでなく、地面がコンクリートで覆われヒートアイランド現象が顕著な都市部では、気分的な効果も相まって、涼しさを感じることができるはずです。
問題は、どんな水を使うのかです。水道水をそのまま撒いたのでは貴重な水資源の浪費と言われかねません。水道水が供給されるまでに排出されるCO2を考えても好ましくはありません。打ち水大作戦では、市から提供される雨水を浄化した水を使っています。

打ち水イベントには、「埼玉打ち水の環」という取組もあります。夏の期間に各職場や学校などで、それぞれが水道水以外の水で打ち水を行い、それをSNSで専用サイトに投稿してもらいます。各地の取組を共有して、環境への想いを繋げていこうというものです。私の職場でも雨水を貯めた水を使って毎年参加しています。雨樋を切り回せるようにしておいて、雨が降る
と100ℓ程のポリ容器に雨水を貯めています。打ち水で余った雨水は、花壇の水やりにも使っています。このように、雨水に利用目的があると、実は雨の日も少し嬉しい気分になるものです。太陽光発電を付けたご家庭では、晴れてどんどん発電されるような日はなんだか嬉しい気分になるという話を聞いたことがあります。雨水利用も、それと同じなのでしょう。

実は、雨水利用は20年近く前から注目されており、墨田区などが先進地域として知られています。2014年には、水資源の有効利用と下水道や河川への雨水の集中的な流出の抑制を目的に、国や自治体の責務を明確にし、基本方針などを定める「雨水の利用の推進に関する法律」も制定されています。
近年、集中豪雨やゲリラ降雨などにより、都市河川の洪水リスクが高まっています。加えて、河川に繋がる下水道や排水路などのインフラの老朽化も深刻化しています。雨樋の先に雨水貯留槽を設ければ、屋根に降った分の雨の流出量を減らせ、流出時間を遅らせることが可能となります。貯留した水は晴れた日に打ち水や植木・花壇の散水などに活用できます。
気候変動問題が現実化する今日、各家庭や公共施設の屋根は太陽光発電による分散型発電所として注目されていますが、屋根は雨水集水装置としても有効です。「温故知新」、気候変動の緩和策としても、適応策としても、雨水利用に今一度、注目すべきではないでしょうか。

【筆者プロフィール】
星野 弘志 氏 (NPO法人環境ネットワーク埼玉 代表理事)
元埼玉県環境部長。現在はNPO法人環境ネットワーク埼玉(埼玉県地球温暖化防止活動推進センター)の代表理事、埼玉県環境科学国際センター客員研究員を務めるほか、埼玉グリーン購入ネットワーク会長、埼玉環境カウンセラー協会副会長などとして幅広く環境啓発活動などに取り組む。
◎星野氏経歴の詳細はこちら: (環境カウンセラーのサイトに移動します)
https://edu.env.go.jp/counsel/counselor/2012111001
◎こちらもチェックしてみてください ↓↓↓
埼玉県環境科学国際センターHP: https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/index.html
公式Facebook:https://www.facebook.com/saitama.kankyokagaku
公式インスタグラム:https://www.instagram.com/cess.saitamaken/?hl=ja
公式Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCloUEno4mbrzZlOT2SzEV7A